概要
1922年、作者のイーデン・フィルポッツが61歳の時の作品。江戸川乱歩による「万華鏡賛辞」によってか、海外よりも日本での人気が高いという作品です。
あらすじ
休暇でダートムアにやってきた、スコットランド・ヤードの名刑事マーク・ブレンドン。しかし、休暇を楽しんでいた彼のすぐそばで殺人事件が起こる。あまり乗り気ではなかったのだが、調査の依頼にやってきた被害者の妻というのが、以前出くわした絶世の美女であったことを知り…
みどころ
乱歩の「万華鏡賛辞」が本当にその通りです。この作品のみどころが、しっかりと書かれていると思います。それに付け加えるべきものはないようにも思えるのですが、乱歩の紹介文に沿って、個人的にみどころを書いてみます。
最初はちょっと退屈ですが、美しい風景描写。そしてそこには恋愛要素もあります。まぁ、30も過ぎて中学生みたいなことやってんじゃないよ、とも思いたくもなりますが、それは温かい目で見てあげましょう。
次に、中終盤にかけてのサスペンスあふれる展開。犯人と探偵の知力と知力のぶつかり合い、それまで押され気味だった探偵チームの反撃開始です。犯人を罠にかけようとするところが最高に格好いいです。そして最後は、驚きの真相です。ハラハラドキドキが止まりません。
読後しばらくたつと、登場人物のそれぞれについていろいろ思うところが出てきます。肉体を持った人間のようにも思えてきます。そしてまた読み直すことになります。すると再読時には、登場人物たちの本当の心の内が感じられて、さらに面白く読めるんですね。
この作品は二度目こそが本番かもしれません。
登場人物
- マーク・ブレンドン(スコットランド・ヤードの刑事)
- マイケル・ペンディーン(元貿易商)
- ジェニー・ペンディーン(マイケルの妻)
- アルバート・レドメイン(ジェニーの叔父、書籍蒐集家)
- ペンディゴー・レドメイン(ジェニーの叔父、元船長)
- ロバート・レドメイン(ジェニーの叔父、元大尉)
- フローラ・リード(ロバートの婚約者)
- ジュゼッペ・ドリア(モーターボート操縦士)
- アッスンタ・マルツェッリ(アルバートの家政婦)
- エルネスト(アルバートの召使い)
- ヴィルジーリオ・ポッジ(アルバートの友人)
- ピーター・ギャンズ(アルバートの友人、引退した刑事)
- ハーフヤード(プリンスタウン警察署の署長)
- ダマレル(ダートマス警察の署長)
どの登場人物も素晴らしく生き生きとしています。誰をとっても捨てキャラがいません。これだけの人物をしっかりと書き分けられるのは、本当にすごいです。特にレドメイン兄弟のそれとなく感じられる、性格の違いが面白く感じました。
個人的にはその中でもベンデイゴーがお気に入りです。最初の気難しい様子から、徐々にブレンドンのことを気に入って仲良くなっていく様子が、微笑ましいですね。
警句・ことわざ
この作品には多くの警句やことわざが出てきます。面白いなぁと思ったものを抜き出してみました。
- だれもがみな、世間にその名を馳せるまではうぬぼれる権利がある
- 黄金が口を開けばだれもが沈黙する
- 計画は人にあり、決裁は神にあり
- どんな犬も自分の犬小屋じゃ百獣の王ライオンですからね
- どんな逆風でもだれかの得になる
- 猫に手袋をしたら、鼠をとらなくなる
- 芸術が存在するのは、あまりにも多くの真実から人間を救うためだ
- より善いはつねに善の敵であり、最善は殉教者か英雄にのみ使われるべき貴重な言葉といえる
- 兎と一緒に逃げながら、同時に猟犬と一緒に兎を追うことはできない
- 新しい箒はいい仕事をする
- 雌鶏から生まれたものはなんでもつつく
ドリアの発言が多いですね。「黄金が口を開けばだれもが沈黙する」はよくわからなかったですが、要は「お金が大事」ということでしょうか。
犯人とトリック
驚愕のトリックだと思います。ですが他の人の感想を見ていると、「犯人やトリックは丸わかり」とかいう意見が多くみられますが、本当に? と思います。
この作品はちょっと特殊で、ところどころで犯人をほのめかす表現があるんです。そこだけを見てそう言っていませんかね。この作品は地の文で犯人をほのめかしつつ、そこから探偵がどんどん離れていくところに妙があるんです。モブ刑事たちの方がまっとうな推理や意見を述べていて、それを名探偵であるブレンドンが切り捨てるところがポイントなんですね。つまりその地の文での正しいほのめかしが、偽の手がかりであるかのように偽装しているわけです。
つまりジェーンを疑った方がいいんじゃないですか、とモブ刑事が示唆していることを含めて、「ジェーンを疑ってくださいよ」という誘導なんです。そこから終盤ではドリアが犯人だという証拠が集まりだします。そして最終的に、ジェーンとドリアのどちらが犯人なのかという謎に集約されていきます。
「ジェーンかと思わせてドリアなの? それともここからまたひっくり返るの?」という感じです。それが実は両方ともが犯人だったという真相なわけです。そこまで見抜いていましたか? またそう考えていたとして、ドリアとマイケル・ペンディーンが同一人物だったことも見抜いていましたか?
第一の事件の時点では、犯人と被害者の入れ替わりを疑うかもしれません。被害者の死体が見つからないというのは、確かに怪しいです。しかし第二の事件において同じ展開を繰り返すことで、その疑惑を薄めています。そして第三の事件においては、迫りくる犯人から被害者を守る展開になっています。ここにおいて、被害者と思われていた人物が犯人だったという最初の疑念は、遠い過去のようにかなり薄れているはずです。
そもそもマイケル・ペンディーンという存在すら忘れているはずです。
そこまであったうえで、「犯人やトリックは丸わかり」なら、それはもう感服します。
つまりこれは「表に見せようとしているけれど、裏なんだろうなぁ… と思わせておいて種類の違う硬貨の表だった」という作品なんです。単に「犯人やトリックは丸わかり」と言っている人は、「表ってわかるじゃんか」という、浅い部分でしか楽しめていないんじゃないかなぁ。そういう意味ではかなり程度の高いトリックを使っているともいえるのではないでしょうか。
あとはこの作品の紹介において、ネタバレが多くあることも問題だと感じます。
ブレンドンがワトソン役で、本当の名探偵はピーター・ギャンズだというのは、紹介でばらしちゃいかんでしょう。それも驚きの一つですし、そのネタバレがあると最初からブレンドンの捜査に疑念を持ってしまいます。
社会派の足で稼ぐタイプの捜査として読めば、ブレンドンのやっていることは普通です。失敗を繰り返しながら、それを修正しつつ徐々に追い詰めていくタイプなんだろうなぁ、と思わせておく。そのうえで、探偵変更からの捜査が根本的に間違っていたという話なのに…
そのネタバレのせいで、評価を落としている部分もあるのではないかとも思います。
ロバート・レドメインを見たドリアの反応
まさか! 見ましたよね──この道のすぐそこに──ロバート・レドメインが!
「まさか!」の部分に違和感があります。
実際にはロバート・レドメインがうろついている前提なのですから、「まさか!」なんて言葉が出るわけはありません。また、前回ロバート・レドメインを見かけたと言ったときは、必死で追いかけたと言っていましたので、本来なら今回も追いかけなくてはいけなかったです。
やれやれ──いったいどうしちゃったんでしょうね、ぼくは! ほこらの影でしたよ!
いや──違いますよ、シニョール。神経をやられてはいませんし、なにも見ていません。ただの影だったんです
何も見ていないというギャンズに合わせる形で、自分も何も見ていないと言ったドリア。
ですが、これは失敗でした。その瞬間は本当に幽霊でも見たのかと思ったのかもしれません。いるわけがないものが見えたからです。しかしその様子をギャンズに観察されてしまいました。また冷静になって考えると、実物として見たのは間違いありません。するとそれがギャンズの作為であることは明らかです。
むしろここは「ロバート・レドメインがいましたよ、追いかけましょう」と言うべきでした。その後の警戒している様子は、そこに考えが至ったからでしょう。つまりこれでドリアは、ロバート・レドメインがそこにいるわけがないと自分が考えていることを、明らかにしてしまったのです。
するとドリアがこれまで言ってきたロバート・レドメイン遭遇の発言は、全て虚偽だったとわかります。そしてその中にはベンデイゴーが生きていた時の、ドリアとジェニーが海岸線を捜索していて、ロバート・レドメインを発見したものもあります。つまりそれはドリアとジェニーが共謀して、虚偽の報告をしていたことになります。
ではドリアが以外の人物がロバート・レドメインと遭遇したものはどうなのでしょうか。ストリー農場のブルックさん、ジェニーと一緒に遭遇したアンスッタ、そして当然ブレンドンも、ロバート・レドメインに遭遇しています。
しかしそれらいずれの場面にも、ドリアは立ち会っていません。ということは、ドリアがロバート・レドメインに変装していたと考えられるのです。
つまりここで全ての真相が明らかになったのです。
感想
本当に素晴らしい作品です。Wikipedia によると、「乱歩没後に評価が下がっていている」とありますが、ちょっと信じられないです。かなり隙が無い作品のように思います。ミスディレクションも適度に使われており、再読時には感心させられます。ブレンドンを埋めようとやってくる二人組の描写なんかは、かなり考えられています。
そりゃ言い出したら、「なんで最後の殺人事件が起こっちゃうんだよ」とか突っ込みどころはあります。そこは犯人の裏をかいて、迷(?)探偵だった彼の名誉を回復させてあげたかった。でもまぁ、それはいいです。それも含めて人間の愚かさと、探偵と犯人の名勝負だったのでしょう。
今回再読してみて、自分が好きなミステリー作品にこの作品との類似点があるとわかりました。それも複数作品にです。
喧嘩している男女が共謀しているという展開です。
それは物語の根幹部分のはずですが、なぜかそれぞれの作品は全く別物として楽しめました。もちろん途中が全然違うのもあるのでしょうけれど、共通部分はむしろベタ展開としてテンプレ化しているまであるのかなぁとか思いました。
漫画などで「これは最後にかつてのライバルが、仲間として助けに来るパターンだなぁ」とラストバトルを読んでいるときにうすうす感じていて、実際にそうなると「待っていました!」となるやつみたいな。ちょっと違うか。
まぁそういうベタ展開のため、古臭いという感じを受けるのもわかります。とはいえ、それだけでは語れないとも思います。英国の文学界の大御所が61歳という年齢において、彼の持ち得る技術の集大成として書かれたものという重みを感じさせるにふさわしい、素晴らしい作品だと個人的には思います。
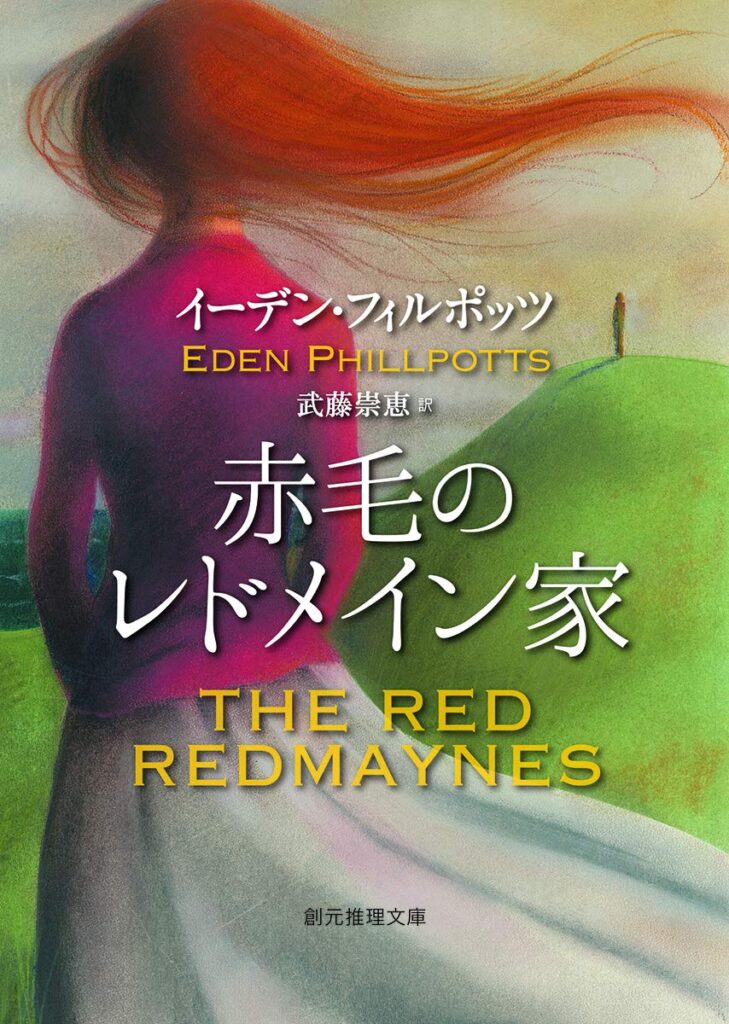

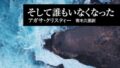

コメント